
文部科学省の学校基本調査(平成17 年)によると、不登校の小・中学生(年間30 日以上の欠席)は、16 万4 千人を超えたと報告されています。
不登校の人数は年々増加傾向にあり、とくに中学生での増加率が大きく、その種類も神経症的不登校だけでなく無気力型の不登校、非行・怠慢型の不登校などが加わり、症状と原因が多様化しています。
このような不登校に対する認識の変化に伴い、不登校対策も多様化しています。
ひとつ目は、「学校に行かない」という生き方を認め、学校にいくという規範そのものを問い直す考えです。
行政や民間、NPO 法人によるサポート校、適応指導教室、フリースクールなどの学校に行けない子どもの「第二の居場所」づくりが進められています。
ふたつ目は、各地域で行われている不登校児を対象とした山村留学やキャンプです。
しかしこれらの「第二の学校」や「第二の居場所」にも参加することが出来ないひきこもり傾向の不登校が増加しており、それが社会的問題になっています。
東京国際大学ではこうした現状を踏まえ、多様化している現代の不登校問題に対応する教育プロジェクトを発足させました。
学校に通うことのできない子どもたちや、「第二の学校」や「第二の居場所」にも参加できない子どもたちのために、東京国際大学では川越市と連携して「第三の居場所」作りをおこなってきました。
スチューデント・サポーター制度の取り組みを含め、「地域子どもサポート委員会委員」に学生を派遣するなど、さまざまな連携を実施しています。
これらの活動では、人間社会学部の専任教員が各専門分野において、学生に対しコーディネート、助言・指導をおこなってきました。
平成19年度よりこの活動をさらに発展させ、不登校児童・生徒の減少、復帰を目的とした「地域連携による不登校予防プロジェクト」を発足させました。
| 川越市社会教育委員として教員を派遣 | |
| 川越市教育委員会と連携して 「学生による不登校児童・生徒支援事業」実施 |
|
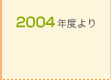 |
川越市「地域子どもサポート推進本部委員」として教員派遣 |
| 川越市「地域子どもサポート委員会委員」として学生を派遣 | |
 |
川越市「地域子どもサポート事業」の普及のため各地域での講演に 教員を派遣 演題「いまなぜ地域子どもサポートが必要か」 |
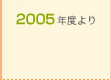 |
川越市教育委員会「小中学生への英会話講座」共催 | 川越市福祉審議会委員として教員を派遣 |
 |
川越市の中学校での学習サポート事業へ学生を派遣 (埼玉県助成による川越市砂中学校での事業) |
川越市教員研修委員として教員を派遣 | 川越市幼児教育審議会会長として教員を派遣 | 川越市福祉関係審査委員として教員を派遣 | 川越市小中学校への日本語ボランティアとして学生を派遣 | 川越市青少年問題協議会委員として教員を派遣 |

