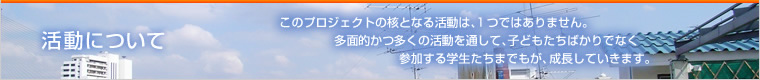学生がスチューデント・サポーターの活動をスムーズにおこなえるように、独自の研修をおこないます。
研修の内容といたしましては、事前指導4回、スーパービジョン1回、事後指導1回の計6回になります。
教育総合相談センターの担当者と東京国際大学教員による事前指導を年4回実施します。
教育総合相談センターによる事前研修の内容は、「川越市の不登校の現状と対応」、 「守秘義務、対応の際の留意点」となっています。
東京国際大学教員による研究内容は「思春期の親子関係と友人関係」、「さまざまな不登校」となっていて、スチューデント・サポーターは出席を義務付けられています。
活動中の学生をサポートするための研修です。
東京国際大学の専任教員が活動中のスチューデント・サポーターに対して個別のスーパービジョンをおこない、現状について助言と指導をおこないます。
事後指導は活動後の学生におこなわれる研修です。
目的としては学生の次の活動への動機付けを高めることです。
これが十分におこなわれない場合、活動が単なる義務となってしまい、「自発的な活動」を意味するボランティア本来の意味が失われてしまいます。
具体的には学生に、家庭訪問などの活動を実施したあとに、毎回、活動報告書を教育総合相談セ ンターに提出してもらい、担当活動終了後は、振り返っての反省とまとめの報告書を提出してもらいます。
そしてその報告書をもとに、東京国際大学のコーディネーター役の教員が学生に個別の事後指導をおこないます。
内容は、活動によって子どもが達成したこと、今後の課題、活動を通じて学生が学んだこと等などです。
 東京国際大学では、地域と連携をとって不登校予防支援の活動をおこなう学生に対して充実したボランティアの教育をおこなえるように、人間社会学部に新規で「ボランティアワーク」という科目を設置し、「地域連携による不登校予防支援プロジェクト」へのバックアップ体制を整えました。
東京国際大学では、地域と連携をとって不登校予防支援の活動をおこなう学生に対して充実したボランティアの教育をおこなえるように、人間社会学部に新規で「ボランティアワーク」という科目を設置し、「地域連携による不登校予防支援プロジェクト」へのバックアップ体制を整えました。
さらに、スチューデント・サポーターが実施するアンケート調査と不登校が生じる背景・予防のメカニズムを分析するためのデータベース化作業についても、情報処理と社会調査士関連の講義などを通して学生に教育をおこなっていきます。
 専任教員が担当する「ボランティアワーク」の科目は、ただ単に学生が講義を受けるだけでなく、ボランティア活動の実習もおこないます。
専任教員が担当する「ボランティアワーク」の科目は、ただ単に学生が講義を受けるだけでなく、ボランティア活動の実習もおこないます。
したがってスチューデント・サポーターの学生は、この科目を履修することによりボランティアを理論と実践の両面から学ぶことが可能となります。
「ボランティアワーク」科目の開講により、学生たちが「地域連携による不登校予防支援プロジェクト」に興味を持って、スチューデント・サポーターをやってみたいと思う学生が増え、活動の輪が広がることが期待できます。